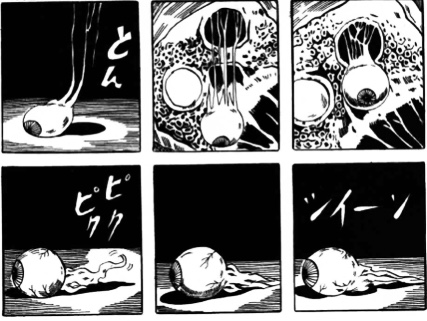なにしろ、全く新しい広告媒体である。専門家などいるわけがなく、作り手はおしなべてアマチュア。暗中模索もいいところで…
これは、facebook について書かれたものでしょうか? それともInstagram?
答えはTikTok・・・
でもなく。
実はこの一文は著書「紋章だけの王国」で、向井 敏さんがTVCMについて語ったものです。
広告を収入源とする電波媒体である民間放送が立ち上がったのは昭和28年、1953年です。
TVCM、テレビコマーシャルの存在をそれまで誰も知らなかったわけですから、当然TVCMは「全く新しい広告媒体」です。ニューメディア。現在を生きている我々からすると想像がつかないような話ですが、そうなんですね。
このニューメディアに試行錯誤で出稿されたTVCMを同時代に見聞きしていた向井 敏さん。私が取り上げたい「広告の見巧者」の一人目です。
ビデオ・テープを使った録画放送が開始されたのが1958年です。つまりそれまでのコマーシャルは必然生放送、生コマが基本だった由。
NHK放送初めての、つまりはTV放送「初めての女優」であった黒柳徹子さんも様々な場で、生放送ドラマの失敗譚を語っています。
テレビ放送は番組もCMも生が基本だったんですね。やり直しがきかない。大変だ。
さてその生コマとはどんな具合だったのか、向井さんが同書で書いています。
松下電器の洗濯機のCMを例に引いてみよう。1953年に作られた最も初期のCMのひとつだが、円筒形の攪拌式洗濯機が、ロング、アップ、俯瞰とカメラアングルを変えながら終始画面を領し、それに女性アナウンサーの説明が入る。秒数は45秒。「ご家庭の労力をはぶくスピードお洗濯。ナショナル家庭用電器洗濯機は、一度にワイシャツ七枚分のお洗濯が、十五分にわずか三十銭の電気料で見違えるように美しくなります。お求めやすい分割払いのお取り扱いもしております。詳しいことは、ご覧のような看板をかかげたお近くの電器店でご相談ください。」この後、「電化による生活文化の向上へ」の字幕。
三十銭!
今のひとは読めますかね、この漢字。サンジュッセンですよ、そこの若人。読める?大したもんです。
一円未満の貨幣が発行停止、通用禁止になったのが1953年、まさに民放の開始年です。
通貨としては使用できなくなりましたが、まだこの頃は計算単位として人々は「銭」に実感を覚えていたんですね。
私が物心ついた頃は、既に銭単位の実感はなく、時々母親が銭のつく話をするのを訝しく聞いた記憶があります。
話を戻します。向井さんはこの頃の松下洗濯機のようなTVCMを「動く商品カタログ」と表現しています。言い得て妙ですね。
45秒という半端なCMの長さは、当時ステーションブレイクが45秒だったことが要因でしょう。
現在のステーションブレイク枠、業界の人はステブレと言いますが、これは1分です。15秒TVCMが4本入ります。
当時生CMの製作にたずさわっていた人たちの記憶を総合すれば、その多くは一分ないしは二分の長尺で、アナウンサーが商品を手に持ち、あるいは傍に置いて、ときに使用方法を実演して見せたりしながら、商品カタログに記されているのとほとんど同じ文句を伝えるだけ、およそ単純平板なものだったという。
このように向井さんは書いています。
ステーションブレイク枠は45秒でしたが、番組内CMは1、2分の生コマ枠が主流だったようです。
今から見ると、とんでもない「動く商品カタログ」TVCMですが、それでも視聴者はこぞってCMに見入り、商品を買いました。
先述の洗濯機と白黒テレビ、冷蔵庫が家電三種の神器と喧伝され、飛ぶように売れた時代の始まりです。
我が家は東京の下町でしたが、家電三種の神器は物心ついた頃にはまだ無くて、母親は家の目の前にある井戸で洗濯板を使って洗濯してい、冷蔵庫も木製のもので氷屋さんに中を冷やす氷板を配達してもらっていたという遠い記憶があります。1964年の東京オリンピックは白黒テレビで観た覚えがあります。
さて高度成長が始まりモノを作れば片っ端から捌けた時代。消費者が、まさに消費することを枯渇していたわけですから。それは売れますよね。
現代と違って、とんでもない粗悪製品が世に溢れていて、婦人家庭誌の「暮らしの手帳」が徹底的な商品テストを行い検証結果をメーカーに忖度することなく誌上公表して部数を伸ばしました時代です。
だからこそ、コミュニケーション上なんの工夫もない、製品カタログのようなTVCMでも、人々はこぞって注視したんでしょう。
向井さんが「動く商品カタログ」と断じた初期の暗中模索時代からTVCMはどのように変わっていったのか…広告の見巧者、向井 敏の見立てを次回にご紹介したいと思います。